会社で頼られ屋の「なんでも担当者」さん必見!
そんな「会社で頼られ屋のなんでも担当者」さんが、2025年も全国のオフィスで奮闘しています。

AIもクラウドも当たり前になった時代。
それでも現場では、「便利になったはずなのに、なぜか仕事は増えている気がする…」
という声も。
この記事では、中小企業の「なんでも担当者」たちが今直面しているリアルな課題10選を、対策ヒント付きでご紹介します。
第1位:「AI導入しろ」と言われても、何から始めていいか分からない

ChatGPT、Copilot、AIボイスボット…。
毎月のように新しいAIサービスが話題になり、「うちも導入してみたら?」と社長から指令が飛んできます。
でも現場としては、「何をAI化すれば業務が楽になるのか」が分からない。
ツールを比較しても、価格も機能もバラバラで、調べるだけで1日が終わってしまう。
対策のヒント
いきなりAI全体を導入しようとせず、「1つの業務にAIを当てはめる」ことから始めましょう。
例えば「通話文字起こしAI」や「自動要約メール」など、見える成果が出やすい領域。
成功体験を小さく積み重ねることで、AI導入が現場の味方になります。
第2位:トラブル対応が多すぎて、本来業務が進まない

LANが遅い、プリンタが止まった、VPNが切れる…。
気づけば朝から晩まで「呼ばれた場所に駆けつける」だけで1日が終わる。
「なんでも担当」さんがいる会社ほど、頼られすぎてキャパオーバーになりがちです。
対策のヒント
小さなトラブル対応こそ、仕組みで減らすのが現実的。
TeamsやSlackなどのチャットツールに社内FAQを作る、
AIチャットボットを設置して「まずここを見てね」という流れを整えるだけでも大きな効果。
自分が動かなくても回る仕組みを、少しずつ育てていきましょう。
第3位:社内システム・アカウント管理が人手依存

Microsoft 365、Google、勤怠、経理、チャット…
「どの社員がどのシステムを使っているのか」が分からず、退職時のアカウント削除漏れが頻発。
クラウドが増えたことで便利になった反面、管理が分散して責任の所在があいまいになるのが2025年の大きな課題です。
対策のヒント
まずは、全アカウントを見える化する一覧を作ること。
Excelでも十分です。
そこから「誰が何を」「いつまで使うか」を可視化し、更新・削除のルールを明文化。
SSO(シングルサインオン)やIAMツールを導入すれば、さらに一元管理が可能です。
第4位:電話・FAX文化がまだ根強く残る

「AIがどうの」と言っても、現場ではまだ代表電話・FAX・電話メモが主役。
中小企業では、顧客の多くが電話を使うため、なかなか「脱・電話文化」が進みません。
結果として、電話取次・伝言・折り返し漏れなど、人に依存したコミュニケーションが続きます。
対策のヒント
電話の完全クラウド化は難しくても、AIを補助として組み合わせることは可能。
PBXに音声認識AIを連携し、通話内容を文字起こし→CRMに自動保存する仕組みを作れば、
電話の手間が減り、情報共有の精度も上がります。
第5位:セキュリティ対策を任されるが、正直わからない

ウイルス、フィッシングメール、情報漏えい――
ニュースを見るたびに社長から「うちは大丈夫か?」と聞かれ、
困惑する「なんでも担当」さん。
でも実際、どこまでやれば十分なのかが分からないのが本音です。
対策のヒント
まずは、最低限の3本柱を整えましょう。
① UTM(外部脅威の防御)
② バックアップ(被害後の復旧)
③ 多要素認証(なりすまし防止)
この3つを押さえるだけで、最低限の守りは完成です。
高度な対策より、「確実に守る仕組み」を優先しましょう。
第6位:老朽機器・古いシステムの更新が後回し

主装置、サーバー、NAS、複合機…。
どれも「まだ動くから大丈夫」で先延ばしにしているうちに、突然の故障。
結果、全社が止まり、担当者の責任のように扱われることもあります。
対策のヒント
「まだ動く」より「保守が切れていない」かで判断するのが鉄則。
保守期限の一覧表を作り、次回更新をカレンダーに入れておく。
更新コストを平準化することで、いきなり数十万円の出費を防げます。
第7位:サブスクやクラウドの契約管理が複雑すぎる

クラウドPBX、Teams、UTM、バックアップ…
契約ごとに請求元が違い、更新月もバラバラ。
「どの契約がいつ切れるのか分からない」という悩みが増加しています。
対策のヒント
まずは契約の台帳化。
料金、期間、支払方法、担当者を一覧化しておくだけで、無駄な契約を発見できます。
また、「AIで請求書を自動読み取り→リスト化」する仕組みを取り入れると、
契約管理の自動化も見えてきます。
第8位:社内教育・引き継ぎが属人化

マニュアルがなく、「〇〇さんに聞いて」が口癖。
担当者が休むと業務が止まり、暗黙知が継承されないのが課題です。
対策のヒント
まずは「よく聞かれる作業」から順に動画化・マニュアル化。
スマホで撮った手順動画でも十分です。
最近はAIを使って「動画→手順書」を自動生成するツールも登場。
属人化を少しずつ“仕組み化”に変えていきましょう。
第9位:クラウドとオンプレの共存に悩む

すべてをクラウドに移すにはコストとセキュリティの壁があり、
結局、社内サーバーもクラウドも両方動かす「ハイブリッド運用」状態。
この中途半端さが、設定・バックアップ・権限管理を複雑化させています。
対策のヒント
「どこに、どんなデータがあるか」を棚卸しするところから。
機密性の高いデータはオンプレ、日常利用はクラウド、というように
「住み分け」を明確にすることでトラブルを防げます。
そしてPBXのように、「基盤はオンプレ、AI機能はクラウド」という構成も有効です。
第10位:「あなたがいないと回らない」と言われ続けている

一見ほめ言葉。でも裏を返せば、属人化の最終形。
体調不良や家庭の事情で休めない、休日も電話が鳴る――そんな担当者は少なくありません。
対策のヒント
仕事を「仕組みに預ける」発想を。
ルール化、タスク管理、AIやクラウドサービスを使った業務の分担化・自動化が鍵です。
いずれは「頼られる人」から「仕組みを整える人」へ。
真の頼られ屋は、“自分がいなくても回る仕組み”を作る人です。
まとめ

「会社で頼られ屋のなんでも担当者」さんは、
社内のネットワークも、機器も、人間関係も支える「オフィスの縁の下の力持ち」。
2025年は、そんな担当者が「人に頼られながらも、AIに助けられる」時代です。
トラブル対応に追われていた時間を、仕組みづくりの時間に変えていきましょう。
「なんでも担当者」のあなたへ。NIKはその努力を知っています
誰に頼まれたわけでもなく、会社のネットワークを守り、
電話を直し、LANを整え、社員の「困った」に応えてきたあなた。
そんな「会社で頼られ屋のなんでも担当者」さんが、
もう少し楽に働けるように
NIKは、AI・PBX・LAN・セキュリティなど、
オフィスのあらゆる仕組みを「まるごと支える」会社です。
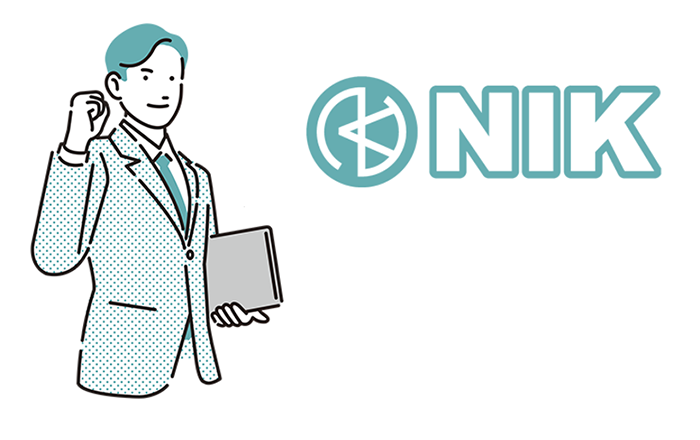
技術の話でも、運用の悩みでも、まずは気軽に話してください。
「できること」より、「一緒に考えること」から始めるのがNIK流です。
あなたが「頼られる存在」であり続けるために、
その頼られ屋さんを、私たちが支えます。








